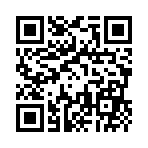2009年02月15日
飛騨の顔
 で、
で、坂口安吾の「飛騨の顔」というエッセイをはじめて読んだのは大学生の頃。
これには衝撃を受けましたねぇ~~~ 彼のその他の作品も、ここから本格的に読み始めました。
ペーパーレスの21世紀とは便利なもので、そのエッセイはこちらで読むことができます。
私が「部外者の目で見る飛騨」を意識するようになったのも、この作品の所為でしょう。
上記リンク先から文章を引用させていただきましょう。
奈良、平安初期には、逃亡したヒダのタクミの捜査や逮捕を命じた官符が何回となく発せられていますが、特に承和の官符には、変ったことが記されております。即ち、
「ヒダのタクミは一見して容貌も言葉も他国とちがっているから、どんなに名前を変え生国を偽っていても一目で知れる筈である」
という注目すべき人相書様の注釈がついているのです。
これによって考えると、ヒダ王朝の王様の系統と、タクミの系統は人種が違うようです。ヒダ王朝系統は楽浪文化を朝鮮へ残した人々の系統で、蒙古系のボヘミヤン。常に高原に居を構え、馬によって北アルプスを尾根伝いに走ったり、乗鞍と穂高の間のアワ峠や乗鞍と御岳の間の野麦峠を風のように走っていた。その首長は白馬に乗っており、それが今も皇室に先例をのこしているようだ。したがって、彼らは現今その古墳から発見される如くに相当高度の文化を持っていたが、居住の点では岩窟を利用したり、移動的テント式住居を慣用したりして、建築文化だけが他に相応するほど発達していなかったようです。またこの一族は山中に塩を探している。海から塩をとることを知らなかったようです。
彼らに木造建築法を教えたのは、彼らとは別系統の人々で、折よくヒダの先住民の中に木造建築文化をもつタクミ一族が居合せたのか、彼らがそれを支那、朝鮮から連れてきて一しょに土着したのか、それはハッキリしないが、人種の系統は別であったろうと思われます。
ヒダのタクミの顔とは、どんな顔なのだろう。一見して容貌も言葉も他国とちがうからいくら偽っても分る、という。それは千百年ほど前の官符の言葉ですが、今でもそんな特別な顔があるでしょうか。ヒダ人は朝敵となって、追われて地方へ分散した者が多いし、他国からヒダへはいって土着した者も多く、千百年の時間のうちには諸種の自然な平均作用があって、ヒダの顔という特別なものがもうなくなっているかも知れない。
しかし、私は戦争中、東京の碁会所で、ヒダ出身の小笠原というオジイサンと知り合った。その顔は各々の目の上やコメカミの下や、目の下や口の横や下などにコブのような肉のもり上りがくッついていて、七ツも八ツものコブが集って顔をつくっている。その中に目と鼻と口があって、コブとコブの間の谷がいくつもあって、そのコブは各々すすけたツヤがあって、一ツの顔ができ上っているのです。
ところが大家族制で有名なヒダの白川郷の写真を見ると、そこのジイサン連の顔が似たようなコブコブと谷間が集ってできてる顔ですね。すると、こういうのがヒダの顔かなア、と私は思った。
この中で安吾が絶賛している、高山市の大雄寺の門前の仁王像は、残念ながら火災で焼失した
そうなのですが、復元されている現在の像も、十分に安吾の話を裏付けるような姿で立っています。
実際、昭和の頃までは菅笠をかぶった「じさま」を高山の街中でも見かけることができましたね。
7世紀というから飛鳥時代。その頃の飛騨には、どんな人たちが住み、どのような生活が営まれて
いたのか?発掘されて復元された頭骨は、飛騨人のものなのか、それとも・・・・・・??
7世紀の頭蓋骨復元 高山
桧山横穴 縄文と弥生の両特徴も
高山市三福寺町の古墳「桧山(ひのきやま)横穴」(7世紀)から出土した約50体の人骨のうち、2人分の頭蓋(ずがい)骨が復元され、市教育委員会が12日、報道陣に公開した。発掘当時、朝鮮半島などから渡来した人の骨と見られていたが、同市教委では「縄文人の特徴と弥生時代以降の特徴も見られる」として、人種が混じり合った可能性を示した。
復元は、日本人類学会会員で、長野市の県立長野南高校教諭、田中和彦さんらが1年がかりで行った。
2個の頭蓋骨のうち、一つは下あごの骨が見つかっていないが、幅約14センチ、奥行き約19センチ、高さ約14センチ。もう一つはほぼ完全で、幅約13センチ、奥行き約21センチ、高さ約19センチ。
いずれも男性とみられ、推定年齢は40~60歳。二つとも、みけんやほおが出っ張っている縄文人の特徴を持つ一方、目と目の間が広い弥生人以降の特徴もあった。頭蓋骨は、4月末まで市郷土館の考古コーナーで展示される。
2009年2月13日 読売新聞 写真もこちらの記事から借用しました。
Posted by まこちん。 at 13:51│Comments(2)
この記事へのコメント
全然検証していないので、想像で物を言っていますが、私も川伝いに広がってきた縄文人と尾根伝いに各地を移動している民族は別ではないかと思っています。
馬が日本に来た時代よりも前にその民族はいて、縄文人と交流していたのでは…と考えています。
縄文時代は長いので初期に入ってきた人たちが山岳民族になったのか、別のルートで入ってきて定住したのかどちらかではないでしょうか?
飛騨は内陸で閉鎖的だったので古い血が残されたのかも分かりませんね。
馬が日本に来た時代よりも前にその民族はいて、縄文人と交流していたのでは…と考えています。
縄文時代は長いので初期に入ってきた人たちが山岳民族になったのか、別のルートで入ってきて定住したのかどちらかではないでしょうか?
飛騨は内陸で閉鎖的だったので古い血が残されたのかも分かりませんね。
Posted by かぜおやじ at 2009年02月18日 18:43
>又次郎Ⅵさん コメント返し遅くなりました
スミマセン。
一応ご希望通り削除しておきますね。
スミマセン。
一応ご希望通り削除しておきますね。
Posted by まこちん。 at 2009年04月04日 10:53
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |