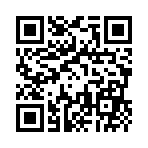2008年05月03日
旧暦の季節感覚

飛騨では、端午の節句は6月5日になっていて、
桃の節句は4月3日、七夕は8月7日と、
暦より一ヶ月遅れて行います。他に東北地方
などでも、同じような風習を守っている場所があります。
これは、「旧暦」の行事の季節感覚に合わせようとして
わざと暦(と書きましたが、正しくは新暦の太陽暦)より
一ヶ月後に行うのです。
皆さんは、何故七夕は梅雨の真っ最中に行うのか、
疑問に思ったことはありませんか?星を見上げる行事を、
何もそんな時期にやらなくてもいいのに、梅雨明けの夏に
やれば良いのに・・・と。
旧暦(明治5年まで日本でも使っていた、太陽太陰暦)と新暦の間には、年や季節によって差があるのですが
おおよそ40日程度、旧暦が早いと思ってもらえば間違いがありません。
旧暦の正月(元旦)とは、今の新暦ではだいたい2月10日頃のことになります。
ここまで読んできて、ピンと来た貴方!
そうです、年中行事というのは、もともと旧暦の日付で設定されているのです。
旧暦の7月7日というのは、新暦では8月17日頃、まさにお盆の頃に当たるんですね。
この頃は天気も安定し、さらにちょうど天高く天の川が昇ってくる季節なのです。
だから桃の節句は、4月13日頃(この頃は、確かに桃の花が咲きます!)であり、
端午の節句は6月15日頃で、この頃に菖蒲の花は見ごろになります。
年賀状に「新春」と書くのは、2月10日頃なら春の兆しが現れてくるから。スゴイ!
寒くて雪深い飛騨や東北地方で、新暦3月3日には露地の桃の花など絶対に咲きません。
それどころか、まだ雪に覆われている地方も多くあります。
そのため、明治になって「では妥協案として、一ヶ月遅れでやろう、そうすれば季節感も
大体合うし、花も咲き出す季節だからなんとかなるでしょう。」という事になったんですね。
ちなみに、春の高山祭りも、明治5年以前は「旧暦の3月14,15日」に行っていました。
今なら4月24,25日頃。そう、ちょうど高山の桜が咲く頃の時期を選んでいたのです。
何故春の祭りは4月14,15日なのか、その理由がこれです。昔の高山の人は風流なんですよね。
花見がてらのお祭。その名残が「ごっつぉのお呼ばれ」に残っています。
これから「旧暦」に気をつけて、行事を見てみると、「だからそうなんだ!」という発見があるかも?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
古民家に和紙の巨大こいのぼりお目見え 高山
春の高山市をこいのぼりや五月人形で飾る「第10回飛騨高山端午の節句」が1日、市内60カ所で開幕した。飛騨地方の端午の節句にあたる6月5日まで行われる。
高山陣屋などの観光名所や旅館、旧家をギャラリーに見立てて、武者人形やこいのぼりなどを展示する観光イベント。春の訪れが遅い同地方では、1カ月遅れて節句を祝うことが習わしとなっている。
同市上岡本町の観光施設「飛騨の里」では、4棟の古民家でこいのぼりを揚げた。
また、旧西岡家の家屋内では、同市上一之町の老田酒造店から寄付された和紙製の特大こいのぼりを初めて展示。昭和初期に職人が手掛けた逸品で、全長9・5メートル、目玉の大きさは50センチもあり、訪れた観光客らが驚いた様子で見入っていた。
5月2日 岐阜新聞Web
Posted by まこちん。 at 11:20│Comments(4)
│徒然に思ったこと
この記事へのコメント
興味をそそる記事でした。
年中行事はやはり旧暦のままでやってほしいですね。
年中行事はやはり旧暦のままでやってほしいですね。
Posted by (  ̄∀ ̄ )にやりねも at 2008年05月08日 20:21
at 2008年05月08日 20:21
 at 2008年05月08日 20:21
at 2008年05月08日 20:21旧暦の行事は中国直輸入の物も多いので、中国の気候との差で合わないものもあるようですね。飛騨地区はさらに合わないので独自(一月遅れ)の方法を編み出したんですね。一つの暦では全国的な整合性は難しいと思います。
Posted by もいもい at 2009年01月22日 11:48
旧暦の平年は太陽暦比11日短いので平年が続くと2年で24日季節が早まります。、だから平均2.7年に一度閏月を入れていっきに戻すのです。
旧暦上、今年の今日と、一昨年の今日とでは、太陽暦でいうと一ヶ月近い差がある という暦が季節感に忠実だというのは暴論ですね。
旧暦には旧暦の良さがありますが、欠点も認識しないと。
旧暦上、今年の今日と、一昨年の今日とでは、太陽暦でいうと一ヶ月近い差がある という暦が季節感に忠実だというのは暴論ですね。
旧暦には旧暦の良さがありますが、欠点も認識しないと。
Posted by あいこう at 2009年05月20日 13:05
>もいもいさん、あいこうさん
暦に正解なんてないんですよ。という前提で
>太陽暦でいうと一ヶ月近い差がある という暦が季節感に忠実だというのは暴論ですね。
はい、閏月の事も含めて「感覚的により近い」
というだけのことです。
文章のどこにも「忠実」とは入ってませんよね。
旧暦そのものを知らない人に、なぜ飛騨の
端午の節句は6月5日にやるのかという理由を説明する場合、こう言うしかないですから。
太陰暦と太陽太陰暦の違いとかメトン周期とかは最初から言っても混乱するだけで、
このエントリのタイトルにもそぐわないですしね。
しかし農耕暦としての太陽太陰暦は、ほぼ信頼に足るもので、でなければ季節変化の激しい日本で1000年以上主暦として採用されません。
その上で、その年の気象条件によっても前後することですから、もともとアバウトな部分を含んでいます。「芒種」だからその日に種蒔こう、とは考えませんが、芒種が近付くと種まきの準備をする。そういう感覚ですね。
暦に正解なんてないんですよ。という前提で
>太陽暦でいうと一ヶ月近い差がある という暦が季節感に忠実だというのは暴論ですね。
はい、閏月の事も含めて「感覚的により近い」
というだけのことです。
文章のどこにも「忠実」とは入ってませんよね。
旧暦そのものを知らない人に、なぜ飛騨の
端午の節句は6月5日にやるのかという理由を説明する場合、こう言うしかないですから。
太陰暦と太陽太陰暦の違いとかメトン周期とかは最初から言っても混乱するだけで、
このエントリのタイトルにもそぐわないですしね。
しかし農耕暦としての太陽太陰暦は、ほぼ信頼に足るもので、でなければ季節変化の激しい日本で1000年以上主暦として採用されません。
その上で、その年の気象条件によっても前後することですから、もともとアバウトな部分を含んでいます。「芒種」だからその日に種蒔こう、とは考えませんが、芒種が近付くと種まきの準備をする。そういう感覚ですね。
Posted by まこちん。 at 2009年05月22日 11:27